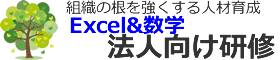「適性検査なんて対策本で勉強してくるから、みんな似たような点数になってしまう」「結局は暗記ゲームではないか」——採用担当者からよく聞かれる声です。
しかし、本当にそうでしょうか。適性検査対策を長年手がけてきた私たちが見てきた現実は、少し異なります。実は「対策される」ことにも、意外なメリットがあります。
1. 対策への取り組み方で見える「仕事への向き合い方」
適性検査の対策をきちんと行ってくる人材は、実は貴重な存在です。
なぜなら、効果的な対策には計画性が必要だからです。「いつまでに」「どの分野を」「どの程度」学習するかを決めることは、まさに仕事でプロジェクトを進める際に求められるスキルと同じです。
私たちが指導してきた受講生の中にも、最初は点数が低かったものの、継続的な学習によって大幅なスコアアップを実現した方が数多くいます。そうした方々は、入社後も同様に地道に業務に取り組む可能性が高いと考えられます。
2. 「一夜漬け」では通用しない仕組み
「対策本を読めば誰でも点数が上がる」と思われがちですが、実際はそれほど単純ではありません。
例えば、SPIの文章問題では表面的には「四則演算」しか使いませんが、文章を正確に読み取って式を立てる力が必要です。これは短期間では身につきません。
玉手箱の図表読み取り問題も同様です。グラフから数値を読み取るだけでなく、何と何を比較しているのかを瞬時に判断する力が求められます。
つまり、真の意味での対策には基礎力の向上が不可欠であり、短期間の詰め込み学習では限界があります。
3. 数学力は「コミュニケーション力」の一部
「文系中心の職場だから数学は関係ない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、適性検査の数学的な問題で測られているのは、計算の速さだけではありません。
- データから必要な情報を抽出できるか
- 物事を論理的に整理できるか
- 複雑な状況を構造化して理解できるか
これらはすべて、日常業務で必要な能力です。会議で数値資料を扱う際、企画書を作成する際、顧客への説明を行う際...数学的思考力の有無によって、コミュニケーションの質は大きく変わります。
4. 読解力不足が業務効率に与える影響
見落とされがちなのが、国語力の重要性です。
適性検査の言語問題で得点できない人材は、実務においても課題を抱えることが多くあります。メールの内容の誤解、指示書の読み飛ばし、会議での議論の理解不足などが発生し、結果として確認作業や説明に余計な時間を要し、チーム全体の効率が低下してしまいます。
5. 企業による対策支援の効果
最近では、部署ごとに適性検査の対策講座を導入する企業も増えています。
一見するとコストのように思えますが、これは実効性の高い投資です。基礎的な算数・国語力の向上は業務品質の向上につながり、論理的思考の習慣化は報告書の質向上にも寄与します。
同じ機会を提供しても、積極的に取り組む人材とそうでない人材がはっきりと分かれます。この違いも、重要な人材評価の指標となります。
適性検査対策による向上は望ましい結果
つまり、適性検査の点数向上は、その人材が以下の能力を有することの証明といえます。
- 計画的な行動力
- 継続的な努力の習慣
- 基礎的な読み書き・計算能力
- 論理的思考の素養
「対策されるから意味がない」のではなく、「適切な対策を行って点数を向上させる人材こそ、組織が求める人材」と捉えることができます。
適性検査は、基礎能力だけでなく、学習姿勢や自己改善への意欲まで総合的に評価できる優れたツールだと、私たちは考えます。

2003年からパソコン指導、2011年から大人向け算数・数学教室「大人塾」を運営。これまで1万人以上にカリキュラムを提供し、企業向けEラーニングも展開。
「学習者中心主義」をモットーに、解説→問題の個別学習で「取り残されない学び」を提供。できない人もできる人も自分のペースで学習できる環境づくりに取り組んでいる。
主な著書
- 『コレ解ける? 数字がこわくなくなる おとな算数ゆるトレ』(インプレス・2025年)
- 『史上最強のNMAT・JMATよくでる問題集』(ナツメ社・2017年)
Web担当者Forumでの連載「数字が苦手なWebマーケター向け算数基礎講座」は累計300万PV突破。